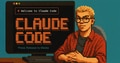読売新聞 対 Perplexity訴訟から考える生成AIと著作権の今 ~権利保護と技術革新の狭間で~
2025年8月7日、読売新聞社が米国のAI検索サービス「Perplexity」を著作権侵害で提訴しました。約21億7000万円という巨額の損害賠償請求と、日本の大手報道機関による初の生成AI企業提訴という事実は、AI時代における著作権保護の重要な転換点を示しています。
こうした動向の裏には著作権法第30条の4(享受を目的としない利用)と第47条の5(軽微利用)という2つの条文をめぐる、より深い構造的な問題が存在しています。
本記事では、上記記事に引き続き最新の法解釈動向と、米国での画期的判例(Thomson Reuters対Ross Intelligence事件)なども踏まえ、この訴訟が示す日本の生成AI政策の課題と今後の展望について、包括的に分析します。
※この記事の音声まとめはこちら
目次[非表示]
- ・1. 訴訟の概要:何が問題となっているのか
- ・2. 2024年7月以降の著作権法解釈の大きな変化
- ・3. 国際的な判例動向が示す新たな潮流
- ・米国Thomson Reuters対Ross Intelligence事件の衝撃
- ・中国・円谷プロダクション対AI企業事件の先駆性
- ・ChatGPTの「ジブリ風」画像生成は著作権侵害か?
- ・実務上のリスク評価
- ・推奨される対策
- ・結論:技術と法の新たな調整期
- ・4. Perplexity訴訟が突きつける根本的な問題
- ・5. 2025年の新たな動き:AI新法と産業政策の転換
- ・6. 各ステークホルダーの最新動向
- ・7. 今後の展望:3つのシナリオ
- ・まとめ:転換期における日本の選択
1. 訴訟の概要:何が問題となっているのか
事実関係の整理
読売新聞社の発表によると、Perplexityは2023年9月から2024年6月までの間に、読売新聞オンライン(YOL)から11万9467件もの記事情報を無断で取得し、自社のAI検索サービスで利用していたとされています。同社は記事1件あたり1万6500円の損害賠償を求めており、今後の調査次第では請求額がさらに増える可能性もあります。
Perplexityの問題行動
特に問題視されているのが以下の3点です:
- ステルスクローリング: robots.txtでAI学習を拒否しているサイトからも密かに情報を収集していた疑い
- ゼロクリック検索問題: ユーザーが元のニュースサイトを訪問せずに情報を得られる仕組みにより、報道機関の広告収入が激減
- 業界ルールの無視: 日本新聞協会が求めるrobots.txtの尊重要請を無視
2. 2024年7月以降の著作権法解釈の大きな変化
文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」の衝撃
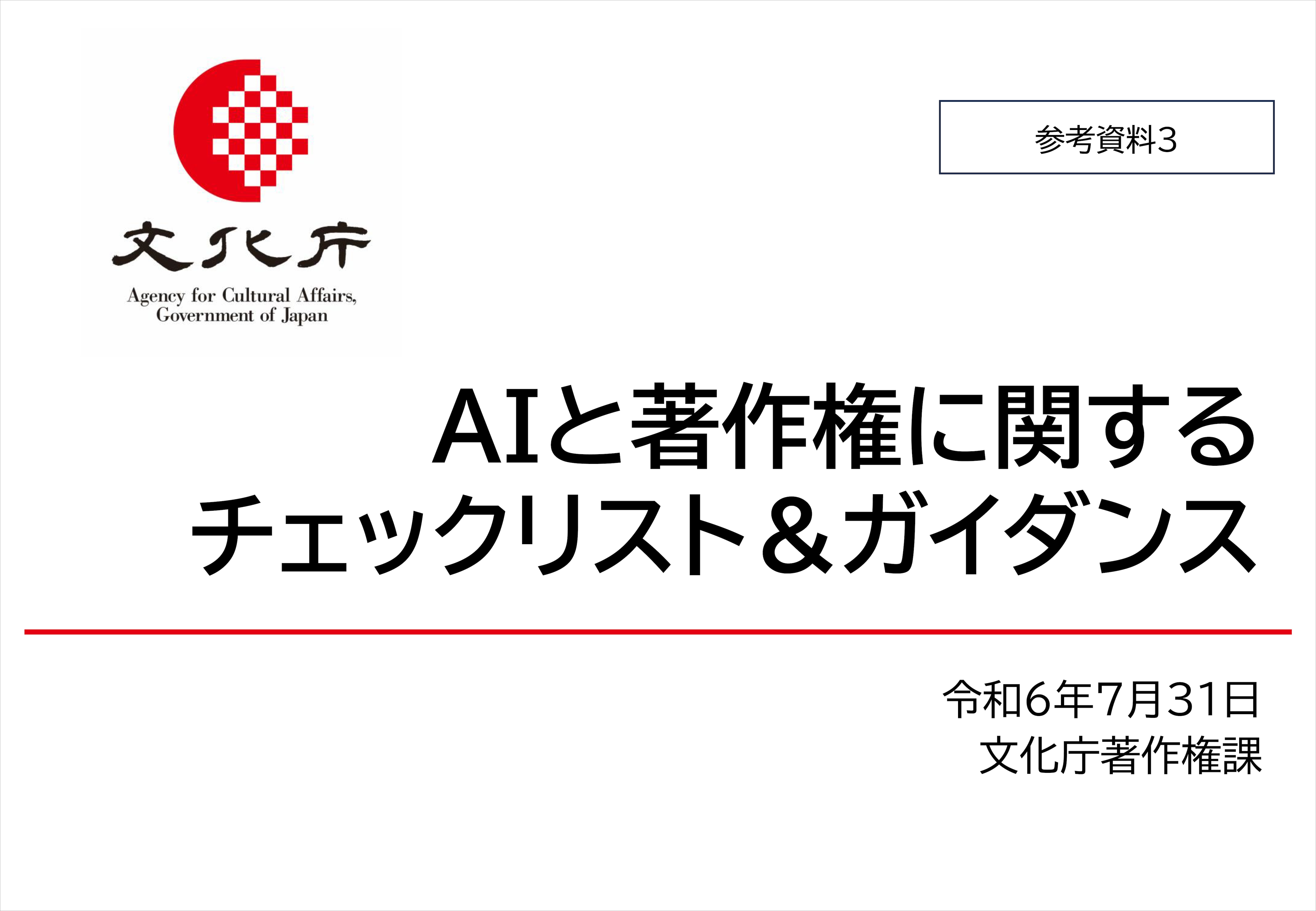
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf
2024年7月31日、文化庁が公表した「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は、AI業界と権利者双方に大きなインパクトを与えました。この44ページに及ぶ文書は、従来の抽象的な法解釈を、実務レベルで適用可能な具体的指針へと落とし込んだ画期的なものです。
特に重要なのは、ステークホルダーを5つのカテゴリー(AI開発事業者、AI提供事業者、AIビジネス利用者、非事業者、権利者)に分類し、それぞれの立場での注意点を明確化したことです。これにより、「誰が」「どの段階で」「何に注意すべきか」が初めて体系的に整理されました。
著作権法第30条の4の新たな解釈基準
「享受目的」概念の精緻化
文化庁の最新ガイダンスでは、「享受目的」を「著作物等の視聴等を通じて視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることを目的とした行為」と明確に定義しました。これは従来の曖昧な解釈に比べ、格段に具体的な基準となっています。
さらに重要なのは、2024年11月22日に更新された「AI事業者ガイドライン第1.01版」において、享受目的の併有について新たな判断基準が示されたことです:
- LoRA(Low Rank Adaptation)等の追加学習:特定の著作物の出力を目的とした追加学習は享受目的ありと判断
- 汎用モデル開発:原則として享受目的なしと判断
- ファインチューニング:その目的と規模により個別判断
「不当に害する場合」の具体例の拡充
2024年7月のガイダンスでは、権利者の利益を「不当に害する場合」について、従来より詳細な例示が追加されました:
- robots.txtの無視:明確に「不当に害する場合」として位置づけ
- ステルスクローリング:正体を隠したデータ収集を問題視
- 過度なサーバー負荷:技術的・経済的損害を与える行為として明記
- 有償データベースの無断複製:商業的価値の侵害として強調
著作権法第47条の5とRAG技術の衝突
日本新聞協会の強い懸念
2024年12月18日、日本新聞協会は「知的財産推進計画2025に関する意見」において、現行の第47条の5がRAG技術に対応できていないと強く主張しました。同協会は、検索連動型生成AIサービスが「情報解析」の概念を超えた利用を行っているとして、法改正の必要性を訴えています。
この懸念は単なる理論的なものではありません。新聞社の記事がAIサービスによって無償で要約・提供されることで、ウェブサイトへのトラフィックが激減し、広告収入やサブスクリプション収入が脅かされるという実害が生じているのです。
第30条の4と第47条の5の役割分担の明確化
文化庁の2024年3月の見解では、両条文の適用関係が以下のように整理されました:
- まず第30条の4の適用を検討:非享受目的の利用か否かを判断
- 第30条の4が適用されない場合に第47条の5を検討:享受目的があるが「軽微利用」に該当するか判断
- 適用要件の厳格性:第47条の5は第30条の4より適用要件が「格段に厳しい」
この整理により、RAGシステムのような技術において、情報検索段階は第47条の5の「情報解析」に該当する可能性が高いものの、検索結果を基にした生成段階では適用が困難であることが明確になりました。
第47条5については、日本新聞協会の解釈が以下にまとまっています。
著作権法第47条の5と新聞記事の利用について Q&A
第30条の4の最新運用状況
2025年8月現在、第30条の4は以下のように運用されています:
- AI学習への原則適用継続:汎用的なLLM開発では引き続き適用
- LoRA等の追加学習への制限強化:特定著作物の再現を目的とした学習は「享受目的あり」として適用外に
- robots.txt無視への厳格対応:文化庁ガイドライン(2024年7月31日)により「不当に害する場合」の典型例として確立
第47条の5のRAGへの適用限界
2025年のRAG実装事例から明らかになった課題:
- 「軽微利用」要件の壁:要約生成や包括的情報提供は「軽微」を超えると判断される傾向が強まる
- AIエージェントへの移行:2025年はRAGからAIエージェントへの技術シフトが加速、第47条の5の適用はさらに困難に
3. 国際的な判例動向が示す新たな潮流
米国Thomson Reuters対Ross Intelligence事件の衝撃
2025年2月11日、米国デラウェア地区連邦地方裁判所は、AI学習における著作物利用について画期的な判決を下しました。法律情報サービス大手のThomson Reutersが、AI企業Ross Intelligenceの法律データベース無断利用を訴えた事件で、裁判所はフェアユースの抗弁を退け、著作権侵害を認定したのです。
この判決の重要性は、以下の点にあります:
- AI学習であっても著作権侵害が成立:技術的処理であることを理由とした自動的な適法化を否定
- 創作的表現の実質的利用:元の著作物の創作的価値との関係を重視
- フェアユースの制限的適用:AI学習への過度に寛容な解釈を戒める
この判決は、日本の第30条の4の「享受目的」概念の解釈にも重要な示唆を与えています。
中国・円谷プロダクション対AI企業事件の先駆性
2022年12月に確定した中国広州インターネット裁判所の判決も注目に値します。「ウルトラマンティガ」と類似した画像をAIで生成・配信した事件で、裁判所は以下を明確にしました:
- AI生成物も著作権侵害の対象:生成段階での責任を明確化
- 類似性による侵害認定:既存著作物との実質的類似で判断
- 将来的な侵害防止措置:技術的対策の実装を命令
ChatGPTの「ジブリ風」画像生成は著作権侵害か?
2025年3月、インターネットを席巻した「ジブリ風」ブーム
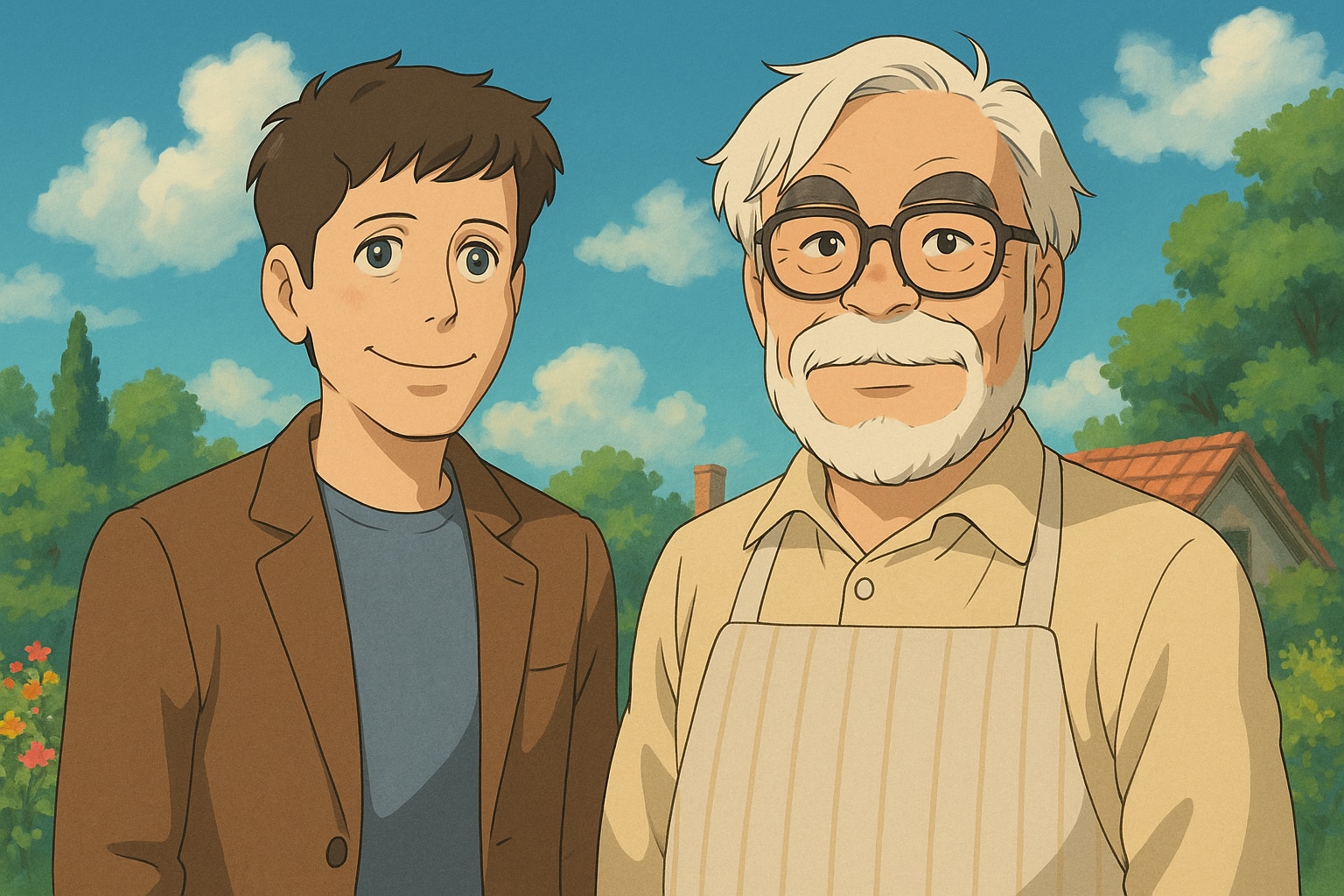
OpenAIがGPT-4oの画像生成機能を無料開放した2025年3月、SNSは「ジブリ風」画像で溢れかえりました。サム・アルトマンCEOが「GPUが溶けるほどの負荷」とツイートするほどの人気でしたが、同時に「これは著作権的に大丈夫なのか?」という議論も巻き起こりました。
アイデア・表現二分論から見た「画風模倣」
著作権法の基本原則である「アイデア・表現二分論」によれば、画風・作風・技法などは「アイデア」の範疇であり、著作権保護の対象外です。福井健策弁護士は以下のように説明します:
「色合いやタッチがジブリ作品に似ているだけで、具体的な画像をコピーしていない『ジブリ風』画像は、画風の模倣であって著作権侵害ではない。これは人間が描いてもAIが生成しても同じです」(弁護士ドットコム取材より)
最高裁判例(ポパイネクタイ事件、平成9年)でも、抽象的概念は著作物として保護されないことが確立しています。
生成AIがもたらす新たな複雑性
しかし、生成AIは従来の「画風模倣」に新たな次元を加えています:
学習段階の問題
- ジブリ作品を含む大量データでの学習は第30条の4により原則適法の可能性
- ただし「権利者の利益を不当に害する場合」は例外
- 米国では複数の訴訟が係属中
生成段階の問題
- 個々の生成画像と既存作品の類似性が焦点
- 「ジブリ風で」というプロンプトは依拠性の明確な証拠
- 大量生成による経済的影響の懸念
実務上のリスク評価
リスクが高いケース:
- 商業利用(商品化、広告利用)
- 「ジブリ作品」としての偽装表示
- スタジオジブリの利益を害する利用
リスクが低いケース:
- 個人的な楽しみでのSNSシェア
- 明確な創作的付加価値があるパロディ
- 教育・研究目的での利用
推奨される対策
福井弁護士は以下を推奨しています:
- プロンプトで「ジブリ風」を避け、より抽象的な表現を使用
- 生成後に既存作品との類似性をチェック
- 生成プロセスとプロンプトの記録保存
- 信頼できるAIサービスの選択
結論:技術と法の新たな調整期
「ジブリ風」画像生成は、現行法では原則として適法ですが、商業利用や具体的表現の類似には注意が必要です。この問題は、AI時代における創作文化の保護と技術革新のバランスという、より大きな課題を象徴しています。
4. Perplexity訴訟が突きつける根本的な問題
文化庁ガイドラインに照らした評価
2024年7月31日の文化庁ガイドラインに基づけば、Perplexityの行為は明確に問題があります:
robots.txtの無視(第30条の4の適用外)
文化庁は、robots.txtの無視を「権利者の利益を不当に害する場合」の典型例として明示しました。Perplexityの「ステルスクローリング」は、まさにこれに該当します。
RAGによる記事要約(第47条の5の適用困難)
ニュース記事の情報価値そのものを提供する行為は、もはや「軽微利用」とは言えません。日本新聞協会が指摘するように、これは「情報解析」を超えた新たな利用形態です。
ゼロクリック検索問題の深刻性
「ゼロクリック検索」は、単なる技術的な問題ではなく、報道機関の存続基盤を揺るがす構造的な問題です。参議院常任委員会調査室が2024年9月20日に公表した「生成AIと著作権の現在地」でも、この問題の深刻性が指摘されています。
報道機関の収益構造は、ウェブトラフィックに依存する広告収入と、コンテンツへの直接課金であるサブスクリプション収入の2本柱で成り立っています。Perplexityのようなサービスが記事の要約を提供することで、両方の収益源が同時に脅かされるという前例のない事態が生じているのです。
5. 2025年の新たな動き:AI新法と産業政策の転換
AI新法の制定(2025年6月4日公布)
2025年6月4日、「人工知能関係技術の研究開発及び利活用の促進に関する法律」(通称:AI新法)が公布されました。この法律は、著作権法の枠組みを超えた、AI時代の新たな法的フレームワークを提示しています:
- イノベーション促進とリスク対応のバランス:規制一辺倒ではない柔軟なアプローチ
- AI戦略本部の設置:政府全体でのAI政策の統合的推進
- 基本計画の策定義務:中長期的なビジョンの明確化
経済産業省の産業競争力重視スタンス
経済産業省は2025年3月28日に「AI事業者ガイドライン第1.1版」を公表し、過度に厳格な著作権法解釈が日本のAI産業の国際競争力を阻害する可能性を指摘しました。同省は、技術革新と著作権保護の「適切なバランス」を強調し、第30条の4および第47条の5の柔軟な解釈を支持しています。
6. 各ステークホルダーの最新動向
権利者団体の組織的対応
日本新聞協会の戦略的提言
2024年12月18日の「知的財産推進計画2025に関する意見」では、以下の具体的提案が示されました:
- 透明性の確保:AI事業者による学習データの開示義務化
- 対価還元システム:著作物利用に対する適正な報酬制度の構築
- 技術的保護手段の尊重:robots.txt等の意思表示の法的位置づけ強化
各新聞社のAIクローラー対応規約
各新聞社は、自社のrobots.txtやサービス利用規約において、生成AIクローラーに対する明確な方針を打ち出しています。以下、主要各社の規約内容(AI関連の禁止事項)を引用形式で紹介します:
読売新聞オンライン(抜粋)
データマイニング、テキストマイニング等のコンピューターによる言語解析行為当社コンテンツを、クローリング、スクレイピング等の自動化された手段を用いてデータ収集、抽出、加工、解析または蓄積等をする行為生成AI等(人工知能、検索拡張生成、RPA、ロボット、プログラム、ソフトウェアを含みますが、これらに限られません。以下同じ)に学習させる行為(検索等の利用により検索エンジンの生成AI等が結果的に学習することとなる行為を含みますが、これらに限られません)または生成AI等を開発する行為本サービスを情報解析(前項第6号から第8号までの禁止行為を含みます)のために利用することはできません。利用者がこれを希望する場合には、当社と別途ライセンス契約を締結する必要があります。
robots.txtの状況
User-agent: ChatGPT-User
Disallow: /
User-agent: PerplexityBot
Disallow: /
User-agent: Perplexity-ai
Disallow: /
User-agent: Perplexity-User
Disallow: /
ヨミダス(抜粋)
利用者は、生成AI等(人工知能、検索拡張生成、RPA、ロボットを含みますが、これらに限られません。以下同じ)に学習させる目的、または生成AI等を開発する目的で、本サービスを利用(結果的に第三者の生成AI等に学習させることとなる利用を含みます)することはできません。
朝日新聞デジタル(抜粋)
(8)デジタル版について、当社の事前の書面による許可なく、データマイニング、ロボット等によるデータの収集、抽出、解析または蓄積等をする行為 、及びAIの開発・学習・利用またはその他の目的のために、情報・データの収集、抽出、解析または蓄積等をする行為
robots.txtの状況
User-agent: ChatGPT-User
Disallow: /
User-agent: PerplexityBot
Disallow: /
User-agent: Perplexity-ai
Disallow: /
User-agent: Perplexity-User
Disallow: /
日経電子版(抜粋)
日経コンテンツを許可なくデータマイニング、テキストマイニングおよびAI開発を目的としたディープラーニングなどの情報処理、情報解析またはAI学習その他の処理のために、蓄積、複製、加工その他の利用を行うことはできません。
robots.txtの状況
User-agent: ChatGPT-User
Disallow: /
User-agent: PerplexityBot
Disallow: /
User-agent: Perplexity-ai
Disallow: /
User-agent: Perplexity-User
Disallow: /
※robots.txtは各社でほぼ同じものを設定している模様
これらの規約の違いは、各社のAIに対する基本的なスタンスの違いを反映しています。読売新聞のように明確に拒否を示す社がある一方、日本経済新聞のように条件付きで許可する社もあり、業界内でも対応が分かれている実態が浮き彫りになっています。
出版・音楽業界の連携
日本書籍出版協会(2024年10月)とJASRAC(2024年8月)は、それぞれの業界特性を踏まえた詳細な提言を公表し、業界横断的な連携を模索しています。
技術企業の対応戦略の進化
大手プラットフォーマーの先行的取り組み
Googleは2024年9月に「AI開発における著作権コンプライアンス・ガイドライン」を公表し、社内チェック体制の詳細を開示しました。これは、法的リスク管理と透明性確保の両立を図る先進的な取り組みとして注目されています。
スタートアップ支援の拡充
経済産業省の「AIスタートアップ支援プログラム」(2024年11月開始)により、リソースが限られたスタートアップ企業も著作権コンプライアンスを確保できる環境が整備されつつあります。
7. 今後の展望:3つのシナリオ
シナリオ1:法改正による抜本的解決
知的財産戦略本部の「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」(2024年5月)では、現行法の限界を認識しつつも、拙速な法改正には慎重な姿勢を示しています。しかし、権利者団体の圧力と国際的な動向を考慮すると、2026年以降、以下のような法改正が検討される可能性があります:
- 第30条の4の適用範囲の明確化:享受目的の判断基準の法定化
- 第47条の5の見直し:RAG技術等への対応を明記
- 新たな権利制限規定の創設:AI特有の利用形態に対応
シナリオ2:市場メカニズムによる解決
法改正を待たず、市場の自主的な取り組みにより問題解決を図るアプローチです。実際、以下のような動きが加速しています:
ライセンス契約の拡大
- 日本経済新聞とOpenAIの提携モデルが他社にも波及
- 包括的ライセンススキームの構築が進行中
技術的対策の高度化
- AIウォーターマーク技術の実装
- ブロックチェーンを活用した権利管理システム
- Content Authenticity Initiative(CAI)の普及
シナリオ3:国際協調による統一基準の策定
2024年8月に施行された欧州AI法や、米国での判例の蓄積を踏まえ、国際的な統一基準の策定が進む可能性があります。WIPOや G7での議論が活発化しており、日本も積極的に関与しています。
まとめ:転換期における日本の選択
様々な流れを見てきましたが、2025年8月現在、第30条・第47条ともに生成AIでの適用に関しては、まだ明確な結論が出ていない状況とえいます。
現在の状況をまとめてみました。
第30条の4(享受目的なし)の適用状況(学習プロセスに適用)
項目 | 適用可否 | 具体例 | 注意点 |
汎用LLM/画像AI開発 | ◯原則OK | ChatGPT、DALL-E等の学習 | robots.txt無視は✕ |
ジブリ作品を含む学習 | △目的次第 | 一般的な画像生成AIの訓練データ | 享受目的の有無で判断 |
ジブリ風LoRA開発 | ✕NG | 特定のジブリ画風再現モデル | 享受目的ありと判断 |
企業内AI学習 | ◯OK | 社内文書でのAI訓練 | 著作物の市場を害さない範囲 |
データ分析用学習 | ◯OK | 市場分析、傾向把握 | 純粋な情報解析目的 |
個人購入書籍のRAG学習 | ◯OK | 自分の蔵書でAI訓練(個人利用) | 私的利用の範囲内 |
第30条の4(享受目的なし)の適用状況(推論・生成プロセスに適用)
項目 | 適用可否 | 具体例 | 注意点 |
ジブリ風画像を個人で生成 | 🟢低リスク | ChatGPTで「ジブリ風の森」生成 | ※「画風」は著作権対象外 |
ジブリ風画像を個人でSNS発信 | 🟢低リスク | X(Twitter)でシェア | 非営利・個人利用 |
ジブリ風画像を法人等でSNS発信 | 🔴高リスク | X(Twitter)でシェア/商品パッケージ、広告利用 | 営利目的はNG |
既存キャラの再現 | 🔴高リスク | トトロそっくりの画像生成 | 複製権侵害の可能性 |
書籍RAG回答の商用利用 | 🟡要注意 | 自社エージェントを構築して顧客にコンサル | 人間が最終的な判断・表現を行う場合は合法判断となるケースが多い |
第47条の5(軽微利用)の適用状況(検索・情報提供サービスに適用)
項目 | 適用可否 | 具体例 | 軽微利用の判断 |
書籍検索サービス | ◯OK | Google Books(スニペット表示) | 数行程度の表示 |
画像検索サムネイル | ◯OK | Google画像検索 | 縮小画像は軽微 |
ニュース見出し | △微妙 | Google News | 見出し程度なら軽微 |
AI検索(要約型) | ✕NG | Perplexity(記事要約) | 要約は軽微を超える |
企業内RAG | △個別判断 | 社内文書検索+回答生成 | 権利者=利用者なら問題なし |
以上がまとめとなります。
第47条は主にGoogleやPerplexityなどの検索サービス提供側の問題となりますが、書籍やインターネット上のデータを元に仕事を行う場合は、多くの方に自分ごととなる事象となります。
これまで書籍を購入し、それを自分で学習して仕事に活かす、というプロセスは合法でしたが、これが生成AIのRAGなどの世界に入ってしまうと一変違法となってしまう可能性もあり注意が必要です(それほどまでに、これまでの社会になかったものが誕生したということです)。
Perplexity訴訟の今後
読売新聞対Perplexity訴訟は、日本が生成AI時代にどのような法的枠組みを選択するかを問う重要な分岐点となっています。
2025年は「AIエージェント」が流行語となり、Claude CodeやCursor等のAIツールも次々と登場。そして本日8月8日には、ついにOpenAIからGPT-5が発表されるなど、技術革新のスピードは加速する一方です。
こうした日進月歩の技術進化の中で、著作権法第30条の4や第47条の5といった既存の法的枠組みは、果たしてどこまで対応できるのでしょうか。文化庁のガイドライン、権利者団体の提言、国際的な判例―様々な動きが同時進行する中、私たちは新しいルール作りの過渡期にいます。
権利保護と技術革新のバランスを見失わないよう、一つ一つの動きをしっかりとチェックしていく必要があります。
この訴訟の行方、そしてAIと著作権を巡る議論の展開を、引き続き注視していきたいと思います。
本記事は2025年8月8日時点の情報に基づいています。生成AIと著作権を巡る状況は日々変化していますので、最新の動向にご注意ください。